【会報コラム】ルーアンの大聖堂とクロード・モネ

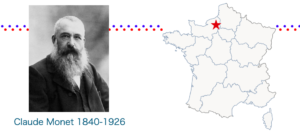
多くの日本の方々が西洋絵画の画家でまず思い浮かべるといったら、クロード・モネはその一人にあげられるだろう?オルセーでも、オランジェリーでもモネは美術館の主役の一人でもある。ルーヴルにも、ほんの少しモネの絵画があるが、そこではちょっと脇役かもしれない。私も例にもれず大昔からモネに魅了されたひとりだ。おそらく最初に目にしたのは上野の西洋美術館と覚えている。その後、モネを追い続けた。アメリカでまずはボストン美術館へ行き、その後、パリの旧・印象派美術館、マルモッタン美術館へ行くのが長年の夢であった。今回はモネがいくつも描いた「ルーアン大聖堂」に触れたいと思う。
ルーアンはガリア時代からセーヌの水運で栄えた町だった。ローマ時代になると、ルーアンに川中島があるのを利用して、ローマ人が橋をかけたため水陸交通の要地として一層発展した。ルーアンのカテドラル(大聖堂)は、聖母マリアに捧げられ、フランスでも屈指の壮大なゴシック建築だ。13世紀に建てられ始め、塔の高さは151メートルありフランス国内では屈指の高さだ。モネが、日射しによって刻々と替わるこのカテドラルを連作で描いたことは知られているかと思うが「うつろう光=瞬間性」をとらえることに全力を傾けた作品である。モネは1892年2月から4月に、さらに翌年にかけて大聖堂を取材し、ほぼ同じ構図の絵を描いた。最初は、晴れの日と曇りの日だけを描き分けるつもりだったが、実際に制作を始めると、朝、昼、夕と刻一刻と変化する光に、すっかり夢中になった。ヨーロッパの大聖堂は西に入口を設けるのが基本である(東をエルサレムに向けるため)。モネはカテドラルの前に並んでいる3軒の商店の2階を順次借り、そこにずらりとキャンヴァスを並べて描いた。太陽の光に合わせて、夜明け直後から夕方まで、様々な時間によって大聖堂の様子が変って行き、30点の連作となった。モネの連作では、他にも積み藁、ポプラ並木、セーヌ河の朝、ロンドンなどがある。瞬間的な光の変化の特異性をとらえようとして、一日に14もの絵を描くこともあった。

モネは前妻カミ―ユと死別し、再婚したばかりの新しい妻アリスにこう書き送っている。
「毎日、僕は描き続けるし、今まで見ることができなかった何かを発見する。なんて難しいのだろう。もうヘトヘトだ。そして、・・・ある夜、一晩中悪夢にうなされたよ。大聖堂が、僕の上に崩れ落ちてきたよ」。モネは2度のルーアン滞在で、この「ルーアンの大聖堂」の連作を描き、後はジヴェルニ―のアトリエで、この連作を完成させた。彼は常日頃、仕事の難しさと自分の遅筆を呪っていたが、この時ほど苦しんだことはなかった。
今までの「ポプラ」や「積み藁」で、うつろう光の自然をとらえてきたモネは「ルーアン大聖堂」の正面の扉口を、その石の壁への光の暗影として描き出している。制作中の手紙で、「全てのものは変化する。たとえ石でさえも」と述べている。生命を持たない石が光によって生き物のように変化する様子を描いたのだ。殆ど同じ構図から、刻々と変化する光の中の大聖堂をとらえ続けたのである。連作は一点一点、バラ色やブルー、グレーなどの光に包まれている。
オルセー美術館所蔵「ルーアン大聖堂、扉口とアルバーヌ塔、満ちる光」は、ほぼ真正面から日差しが当たる夕方の光景と思われる。この作品ではブルーと黄金の調和が美しい。ハレーションを起こしているかのような光の当たる場所と、より暗い部分、日差しの強さや、空気の渇きまで感じられる。モネは描くだけではなく、絵具そのものを厚く盛ることで、中世の建物の荘厳な雰囲気を表している。また、モネは大聖堂の臨場感を出すために、大聖堂の一部を切り取って大胆にクローズアップして、これによって大聖堂が大きく絵の外に広がる効果が生まれるのだった。この辺りが我々日本人の共感を生む要素ではないだろうか?部分を描いて全体をイメージさせる日本美術の手法をモネが取り入れたものだからであろう。

その後、95年6月にリュエル画廊の個展で20点が展示された。会場に訪れた人々は、その劇的に変化する光の中の聖堂に、息を飲んだという。モネは完成から発表まで1年以上も遅らせ、顧客の購買意欲を巧みに刺激したという。作品をまとめて展示する方法も功を奏した。一枚一枚は独立した作品だが、まとめて見た時に初めて夜明けから日没までの時間の推移を体験できる一つ一つの大きな作品となるのだ。このようなコンセプトの話題性や、購入者が比較しながら作品を選定できるメリットも、モネは考慮に入れていた。こうしたマーケティングも手伝って、ルーアンの大聖堂の売れ行きは上々であった。「ルーアンの大聖堂」の絵は世界中に点在している。お近くの美術館にこの「ルーアンの大聖堂」があったら、もう一度ご覧頂きたい。次にご覧になる際にチョットは違った見方ができることを期待する。
(執筆 星野守弘 フランス公認ガイドコンフェランシエ )
